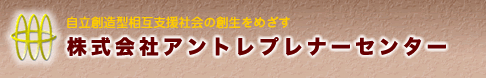活躍する起業家の条件を一言でまとめると、自分の置かれた環境から逃げずに、今、できることから前向きに取り組んできたことといえるだろう。さらに、どうしてそれができたかといえば、それは強い「思い」を持って生きてきたからというほかないのではないか。
もし私たちの人生が環境によって左右されるものであるとするならば、それほど面白味のない人生はないだろう。それでは貧しい家に生まれれば一生貧しいだけ、不況になれば会社もダメになるだけになってしまう。しかし私たちは「思い」という、環境すらコントロールしてしまう力を持っている。つまり、自分の人生をどのような「思い」を持つかによって自由にコントロールすることができるのである。
事業の成否を分ける「思い」
事業において最も大切なのは、「人」であって会社や組織ではない。なぜなら会社や組織をよくするも悪くするも「人」が決めるのであり、会社や組織といったものは「人」が社会活動を営むうえで便宜上つくった仮の存在にすぎないからだ。
ではさらに、人がいさえすればいいかというとそうでもない。そこにどのような「思い」を持った人がいるのかということが重要になる。人は勝手に動くものではなく、「思い」によって動くものだからだ。弱い「思い」しかななければちょっとした障害にぶつかっただけで、その行動は止まってしまうかもしれないが、強い「思い」を持って臨めばどんなに大きな障壁だって乗り越えていくことはできる。
障害があることが問題ではないのだ。何をしたって、それこそじっとしていたって病気やけが、災害といった障害は自分の身に降りかかってくる。大切なことは、そういう障害に対して、自分はどんな「思い」を持って臨むかということである。障害の大きさに対してどれだけ強い「思い」を持ったかで、それを乗り越えられるかどうかが決まる。最も強い「思い」を持つことができれば、乗り越えることができない障害など私たちにはありえない。 |