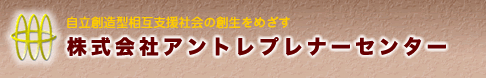|
 |
 |
 |
新経営用語
|
 |
| 1).企業 |
| 社会に貢献し、人間性を向上させるところ。個人個人が持てる能力を最大限に発揮し、自己責任で互いに助け合いながらビジョンの達成を目指す場。企業は利益を出すこと、存在することが目的ではなく、ビジョンの達成を目的とする手段である。企業がその利益や存在を目的とすると、社会的に価値がないことも利益になりさえすればやることになり、さらには真実を隠し、社会に害をもたらすことにつながる。 |
| 2).企業の成長 |
| 社会貢献度を高めること。社会により大きな価値・感動を提供することにより、社会的な存在価値が高まること。単なる規模の拡大や売上の向上、社員の増加は成長ではない。企業の成長が社会に価値・感動をもたらし、顧客や社会を幸せにするものでなければならない。 |
| 3).企業の拡大 |
| 単なる規模の拡大、売上の向上、社員の増加。成長を伴わない拡大は、反社会活動につながり、社会の弊害をもたらす。 |
| 4).起業家精神 |
| いかなる環境条件のなかでも、自らの能力と可能性を最大限に発揮して道を切り開いていこうとする姿勢。あらゆる問題を前向きに受け止め、改善向上の機会とする。さらに自己責任で考え、自分ができることから取り組んでいく。その目的は社会や他人に価値・感動を提供することである。 |
| 5).メンター |
| 相手の持つ可能性を最大限に発揮させる支援ができる人。部下や周りの人々をやる気にさせ、元気にする人。メンターの基本的な姿勢は、自ら見本となって行動し、他人を信頼して支援すること。メンターが重視するのは相手がこちらの言うとおりに行動しているかどうかということであり、そのためにまずは自分自身の行動で示し、どんな相手に対しても信頼の姿勢を崩さず、励まし続ける。メンターは他人をコントロールしようとする管理者とは対峙する関係にある。 |
| 6).メンタリング・マネジメント |
| 個人のやる気を最重要視したマネジメント。企業の生産性はそこにいる人が自発的に能力を最大限に発揮することによって決まるものと考え、その自発性を最重視する。それは個人の意識に焦点を当てたマネジメントである。 |
| 7).アントレプレナー |
いかなる環境・条件のなかでも、社会に価値・感動を提供するために、今できることから自発的に全力でやる人。他人のために自分自身と闘うことのできる人と言うこともできる。
このような起業家精神を持った人のことをアントレプレナーと言う。その意味では起業家精神がなければアントレプレナーと言うことはできない。一方で、サラリーマンであったとしても起業家精神を持っていればアントレプレナーである。 |
| 8).売上 |
| 社会への貢献度が数字化されたもの。売上の向上はそれがどのような理由で伸びたのかが問われる。社員への強制的ノルマや営業外収益などでいくら企業の売上が伸びたとしても、その企業の社会的存在価値があるとはいえない。むしろ社会に価値・感動を提供せずに売上が伸びたとすれば、そのこと自体が問題。社会に価値・感動を提供した結果が売上であり、売上が伸びないのはそれができないだけである。 |
| 9).会社人 |
| 会社に依存して生きているだけの人。会社の指示に対しては忠実だが、自己責任で考え、自発的に行動することはしない。社内のことだけが関心事であり、社外の出来事については無関心。必ずしも社会に貢献できるとは限らないばかりか、働く目的が個人的安楽であるため、その増加は企業ばかりでなく社会を崩壊させる根本的な原因となる。 |
| 10).社会人 |
| 社会に貢献できる人。企業で働くのはそのための手段。より社会に貢献できるようになるために、常に自分自身の能力を向上させることに努力を惜しまない。働く目的は、他人や社会に価値・感動を提供することによって充実した人生をおくることである。 |
| 11).社風 |
| 自分自身が今そこでつくっているもの。社風が暗いのは、周りの人々が暗いからではなく、自分自身が暗いことが本当の原因。明るく元気な人が来ると、その場は明るくなり周りも元気になる。誰がいるかによって職場の雰囲気は変わるものである。ムードメーカーは自分自身。 |
| 12).信用 |
| 継続的な努力によってのみ生まれるもの。この人、この企業ならば必ずやり遂げる、間違いないと相手が信じること。いくら"イメージ"を大切にしても信用は生まれない。なぜなら、信用は"真実"からしか生まれないからである。 |
| 13).組織 |
| 企業活動を効率化するための役割分担、情報伝達経路といった一つのシステム。組織をいくら変革したところで、人々の意欲を高めることにはつながらない。組織を最大限に活かせるかどうかは、そこにどのような意識の人々が集まっているかによって決まる。組織改革と意識変革はまったく別物であり、意識変革とはビジョンの共感者集団を創ることをいう。最も効率的な「システムとしての組織」はビジョンの共感者集団という「意識としての組織」ができてこそ機能するのである。 |
| 14).組織の活性化 |
| 自分が元気になること。今自身がどのような組織にいたとしても、そこでできることを考え実行していくことが、組織の活性化になる。組織が活性化するかどうかは周りの人々がどうかではなく、自分自身が目的に向けて意欲的にチャレンジし、活性化することによって決まるものである。 |
| 15).問題 |
| 改善、向上、成長、飛躍のチャンス。成功する人は問題を喜ぶことができる。問題がなければ、より大きなビジョンを描いて問題を創り出すことが大切。問題がないことが最大の問題である。 |
| 16).安定 |
安定は目指すものではなく、改善・向上してきた結果である。
また、現在の安定は将来の安定をまったく約束するものではない。それどころか、安定を得たと思ったときから、衰退が始まっている。日々変化する社会環境の中では、安定して続ける事業や企業などはありえない。
どんなに安定している状況の中でも改善・向上することが、将来の安定への唯一の道である。 |
| 17).意識変革 |
ビジョンの共感者集団を創ること。依存型意識の集団から自立型意識の集団へと変革すること。企業の規模が大きくなるほど人々は企業に依存し、自発的な行動をしなくなっていく。企業の成長に従って、相反するように人材の活力が失われていくのである。
意識変革とは、このような依存型の意識から自立型の意識への変革をいう。つまり、何かのために、何を目指して働くかを明確化し共有する。そしてそのために一人ひとりが自分でできるように支援することである。 |
| 18).感動 |
感動は、うまくいかないことの先にある。大きな困難があり、不可能と感じる障害があるほどに、その先には大きな感動が待っている。
さらに最大の感動は、自分が努力したことで他人を感動させたときに得られる。 |
| 19).管理 |
| やればやるほど相手のやる気がなくなるもの。管理の強化は短期的な成果の代わりに、経費の増大と信頼関係の崩壊、さらには長期的な生産性の低下を招く。 管理とは決められたことを確実に達成しようとするために社員をコントロールしようとする考え方である。「飴とムチ」によって動機づけ、強制、命令によって行動を促そうとするものだ。しかし管理はやればやるほど相互の信頼関係はなくなり、相手は束縛・限界感の中で、不満とストレスがつのり、次第に生産性は低下していくことになる。 |
| 20).信頼 |
こちらが期待したことを裏切られたり、相手が過ちを犯すことも前提において、相手のすべてを受け入れること。
相手が成果を出せないのは相手が悪いのではなく、自分がきちんとアドバイス、フォローをしていないからだと考える。相手に責任を押しつげず、何度でもあきらめずにチャンスを与え続けることである。
信頼なくして組織、集団の結束はありえない。 |
| 21).信頼関係 |
| こちらから信頼することによってのみ相手からも信頼される。信頼関係がつくれるかどうかは相手が信頼できるこどうかではなく、自分がどれだけ相手を信頼するかによって決まる。信頼関係は話し合ったり、飲みに行ったりすることによって生まれるのではなく、こちらが相手のすべてを受け入れることによって生まれるものである。 |
| 22).支援 |
相手のために役立ちたいという意識を持って、できる限りの応援をすること。そして、最大の支援とは励ますことである。
支援の目的は相手が自発的に困難・問題を乗り越える努力をするようになることである。まず自らが見本となって行動することで相手を動機づけ、相手がどんな状況であったとしても信頼し、できる限りの応援をしながら、長期的視野に立って応援し続けることである |
|
 |
 |
|
 |