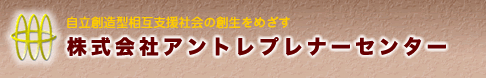|
意識の共有化とは、ビジョンの達成のために自立の姿勢を共有することである。そのためにはまず、言葉を共有化することが必要となる。
同じ言葉であったとしても、そもそもその意味は、人によって多少なりとも違っているものである。そのために同じ行動をとるはずのものが、人によってまったく違う行動をとってしまうこともある。
こんな珍事が起きることがある。
ある上司が研修で自己責任が大切だと聞いて、そのとおりだと思い、自分の職場に帰ってから、「みんな自己責任で考えるようにしなさい!」と言った。
この上司は、部下に自己責任を強制することが他者責任であることに気づかず、まったく正反対の行動を取ってしまったのである。自己責任で考えるならば、「何か問題が起こっても、それはすべて私の責任だ」と言うべきだったのだ。
また、「お客様のためになることを考えよう」というスローガンを掲げたところ、クレームを言ってきたお客様に対して、ある営業マンは「それはあなたの使い方が悪いからです。もっと説明書をよく読んでから使うようにしないと、何を買っても壊してしまいますよ!」とたしなめてしまった。
その営業マンに言わせれば、お客様が自分で問題を解決できるようにさせなければ本当にお客様自身のためにならないのではないか、ということだった。このように、「お客様のためになること」が人によってさまざまに解釈されてしまうのである。
一つの言葉であっても、その意味については、人によって多少違った理解をしているのが普通である。ところが、まったく違った理解をしていると、一人ひとりバラバラの行動をとったり、コミュニケーションにとても多くの時間と労力がかかったりすることもある。よく、議論をしていて、二人の人間がまったく同じ内容のことを、違う表現で主張し合っていることがあるのも、こうした言葉の意味の違いが原因になっている。
このような問題を解決するためには、あらかじめ言葉の意味を一つひとつ正確に共有化しておかなければならない。具体的な事例を掲げてわかりやすく説明したり、共有化すべき言葉の意味を図や絵を使って誰にでもわかるように解説したマニュアルを作成することが必要である。「ここまでやらなくてもわかっているのでは」というくらい詳細にわたって一つひとつの言葉を解説、マニュアル化してちょうどよいくらいになるだろう。そしてOJTの中では、一つひとつの行動を言葉の意味に基づいて日々指導することが必要である。
言葉の共有化の問題は、多国籍の人材が多い海外の企業では、大きなテーマとしてその解決のための努力がなされてきたが、単一民族であるわが園においては言葉は共有化されているはずだという前提でことが進んでしまうために、これまではあまり重視されてこなかった。しかし、企業の中で共に活動するためには、もう一度仕事の現場で使われる言葉の意味を一つひとつ明確化して共有化する必要がある。
なお、本誌の毎月二○日号に連載中の「新経営用語辞典」で、経営上使われる言葉の意味について私なりに解説しているので、参照していただければ幸いである。 |