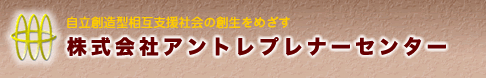自立型人材がその能力と可能性を発揮しやすいシステムとは、個々人の自発性と相互支援の意識を重視し、そのうえでの効率を考えたシステムである。つまり、自分の仕事と社会とのつながり、ビジョン達成に向けて自分の仕事の意義がいつでもはっきりとわかるようなシステムである。
何のためにコピーをとるのか、何のために丁寧な言葉遣いをするのか、何のために電話をするのか、何のために商品を開発するのか、何のために売上をあげるのか、これらすべてと企業のビジョン達成との関係をはっきりと認識できるようなシステムをつくる必要がある。
このような自立型人材がその能力と可能性をより発揮できるようなシステムは無限にあり、考えればいくらでも効果的なシステムを発案することができるだろう。ただし、それらとて万能なものはない。発揮しやすくなるだけで、発揮することを保証できるものはないのである。
このことを前提に、以下に自立と相互支援を促進するシステムについて具体的に考察してみよう。
(1)自己の社会的生産性と存在価値が常に認識できるシステム−仕事の意義が常にわかる
まず第一に取り上げたいのは、自己の社会的生産性と存在価値を認識できるようなシステムである。つまり、自分が今やっている仕事の先にビジョンの達成があることが認識できるようにすることである。
私たちは無意識でいると目先の仕事を終わらせることだけを目的化して、本来の目的、仕事の意義を忘れてしまう傾向がある。
このことを防ぐための基本は、職場で常に仕事の意義をお互いに確認しあうことだ。
「きれいにコピーを取ってくれたおかげで、お客様から見やすいと喜んでいただけたよ、ありがとう」
「この仕事が終わるとまた一歩夢に近づくね」
このように常にお互いが何のために働いているのかを言葉として相手に伝えることで、自分自身も再確認することができる。
また、毎日会社に届く顧客からの感謝の手紙や電話などをすべて社内メールに掲載して、全社員が確認できるようにしておいてもいい。自分たちの仕事が社会にどのように関わっているのかを感じ取ることができるからだ。
さらに、業務日報ではなく他人の仕事で感動したことを毎日提出する「感動日報」という方法がある。これを全社員が相互に行うことによって、自分の存在価値を他人から教えてもらうことができる。
「田村さんが私のミスで起きた問題を自分の責任として解決しようとしてくださっていることにとても感銘を受けました」
「鈴木さんが昨日お客様のために夜遅くまで一人でがんぱっている姿を見かけて感動しました」
「田中さんが朝元気に挨拶してくださったので、自分も元気にがんばらなくちゃと思いました」
これらのように、お互いの存在価値を確認し合うのが「感動日報」である。
いずれにせよ、「自分がいないと困る人がいる」「自分がいることによって、人に喜んでもらうことができる」という感覚を常に社員全員で共有することである。
さらにまた、個人の名前が表に出るようなシステムも面白い。個人の表彰制度などもそのための一つの方法であるが、もう一歩踏み込んで新しい技術や商品にはその開発者の氏名をつけることで、個人の業績・存在価値を明らかにする。
商品そのものではないにしても、社内の開発モードとして、「鈴木式問題解決法」や「田中発想第二八号」などといったものであってもいいだろう。もちろん、開発者が自分でその名称を考えることができるようにしておく。
自分たちのやっている仕事の意義をそのまま名称にすることも、自分の存在価値を認識する一つの方法である。たとえば、総務・管理部を「社員支援部」、営業部を「顧客価値提供部」、開発部を「末来感動創造部」、工事部を「働く姿で感動させる部」などと名称を変えるのである。
これらは自分の存在価値を確認し、個人が組織の歯車の中に組み込まれているという錯覚を防ぐために有効な方法である。
(2)容易に変化できるシステム−常に生産性を高める
環境変化に対応した素早い意思決定を可能にするために組織をプロジェクト型、ネットワーク型に転換する方法がある。このような組織のフラット化は、出世を目的にさせないようにすることも大きな目的の一つである。出世しようにも部課長などの役職をなくしてしまえばどうしようもないからだ。そうではなく個人個人の生産性が問われるシステムなのである。
しかしこのようなシステムで注意しなければならないことは、何のために働くのかということをしっかりと共有化しておくことである。このビジョンの共有化ができていない場合には、組織をフラット化することによって出世などのこれまでの目的をなくした社員は、そこにいる存在意味(アイデンティティ)を見失ってしまう。組織のフラット化は意識の共有化ができていなければまったくの逆効果になることがある。
また、すべての部署やプロジェクトに期限をつけるという方法もある。配属に期限をつけるのではなく、仕事に期限をつけるのである。いつまでにやるのか、どこまでやるのかをあらかじめ決めておくのだ。なぜなら同じことを繰り返すことで仕事をした気にならないようにするためである。仕事とは新たな価値、感動を社会に提供し続けることなのだから。
さらに、社内と社外の境界線をなくすことによって急速に変化する環境に対応できるようにすることもできる。すべての部署の存在価値を半年ごとに見直して、その部署の生産性が低ければ仕事を外注する。たとえば企画部の仕事のレベルと社外の企画会社の仕事のレベルを比較して、社外のレベルのほうが高けれぱ社内の企画部を消滅させ、企画をすべて外注する。その場合は毎年社外コンペで外注先を決める。それはいま外注しているところよりもレベルの高い外注先が現れる可能性があるからである。
このような部署や仕事の外注化は企業間の新しい共存関係をつくる。ベンチャー企業が発案した商品を大企業が商品化して販売したり、自社の生産性の低い部門や社内で対応できない仕事を同業他社に外注したりという新しい関係ができるだろう。新しくできた航空会社が飛行機の機体の整備を、既存の大手航空会社に外注しているのも同じような考え方である。
生産性という観点で見れば社内と社外の区別はほとんど意味がない。たとえ社員であったとしても業界の中でトップレベルの技術、ノウハウがなければ、仕事を託する価値はないと言わざるをえない。なぜなら、その場合仕事は外注化したほうが生産性が高くなるからである。どこの会社に所属しているかよりも、どのレベルの社会的生産性があるのかが問題なのである。
(3)個人の自発性を重視したシステム−すべてを自分で決める
自分で役割を見いだすことができるようなシステムである。つまり不満があれば自分で解決できるような環境をつくることである。
まず、配属に関しては会社がほとんど一方的に社員の配属を決めているのが現状である。そこで社員が自分の意思と努力で自分の配属を決めることができるようにする。
具体的な例としては、仕事は原則として希望制で決める。そのために毎年または四半期ごとに「配属選抜試験」を行う。多くの企業で役職者になるための試験はあるのだから、配属のための試験があってもおかしくはないはずだ。また、その試験は各部署でいま働いている人々に対しても適時行うべきである。なぜなら、いま働いている人々も常に自分の能力を高めていく必要があるからだ。
たとえぱ、経営企画部へ配属を希望する場合は、経営企画に関する社内試験に合格することを条件にする。もちろんこの試験には、すでに経営企画部で働いている人々も同時に同じ条件で受けなければならない。その上位合格者が、次期の経営企画部に配属されるというシステムである。もし第一希望に落ちた場合には、第二、第三希望の職場に挑戦する。もちろん、本人があきらめない限り毎年何度でも第一希望の職場に挑戦できるものとする。さらに、すべてを自分で決めるというシステムもある。これは企業を個人事業主の集合体として考えたシステムである。すべてのことを個人の責任で進めていくのだ。
たとえぱ、営業部を希望するならば自分で営業部を設置して、自らが責任者となり部員を募る。部員が集まらなければ、もちろん一人でやらなければならない。また他の人が始めた営業部に所属してもよい。このように自由に部署ができるので複数の営業部ができた場合は第一営業部、第二営業部といったように二つの営業部が共存することになる。部員の報酬はあらかじめ売上に対する歩合で設定しておく。まったく売上があがらなければ、報酬があるどころか、会社に対して事務所使用料などの社内的負債を負うことになる。また、経理部や総務部などの部門を設置する場合は、社内の他部署を顧客と見なして仕事を受注して売上とする。もちろんその価値がなければ、仕事は受注できないことになる。
これらのような自発性を重視するシステムは、近年積極的に検討され始めている。
(4)他人や他部署を支援するシステム−社内のすべての資源を相互活用する
他人や他部署を支援するためには、まず情報が共有化されていることが前提条件になる。情報が共有化されていなけれぱ、誰に何を支援してよいのかわからなくなるからだ。そうなると、たとえ同じフロアにある他部署ですら何も支援することができなくなり、相互に「隣は何をする人ぞ」という関係ができてしまう。そして情報の共有化とは、情報が提供されるのを待つのではなく、まずは自分から相手に対して情報を提供することである。
また、経営幹部が社員に対して隠し事がないほど、つまり欠点や問題点を知らせるほど経営陣と社員との信頼関係は強くなる。信頼関係を壊さないためにと言って、情報を隠すことはまったくの逆効果である。ここでは経営陣が自らの自己利益を追求する姿勢が唯一の障害となる。
そのために、役員会議を社員に公開するのも一つの方法である。毎回選ぱれたメンバーが役員会を傍聴できたり、意見を述べたりできるようにする。または社内メールでそのすべての内容を公開してもいいだろう。
そして次に、各部門で起きている問題点を毎週社内情報紙を作成して回覧する。これはできれば毎日のほうがいい。その中では問題を抱えて成果を上げられない人や部署の状況をできる限り詳しく掲載する。それに対してみんなでどうしたらよいか、どんな支援ができるかを翌週の情報誌に掲載したり、電話やファクスなどを利用して直接情報提供する。
また、近年急速に活用され始めているイントラネットを使うことによって、以下のようなこともできる。
「困っていること」「支援できること」をイントラネットを活用してお互いに情報交換する。たとえばここでは売上減少に困っている営業部に対して、その他の部署に所属するすべての人がアイデアを提供したり、見込み顧客を営業部に紹介したりする。何もできることがなければ、励ましのメッセージを送る。部下との人間関係に悩んでいる人がいれば、それこそみんなで励ます。
また、個人の得意なこと「得意技ポード(仮称)」を項目別に検索できるようなシステムを組んで設置する。具体的にはあらかじめ自分ができることを趣味や経験などを問わず自由に登録しておく。そうすることによって、たとえば、ドイツから初めてのお客様が来るといった状況の時、ドイツ語が話せる人を社内からこの「得意技ボード」を使って検索して見つけだす、といったことができるようになる。
これらと同じことを関連会社や下請け会社、さらには社外のネットワークの中で利用することができれば、無限の経営資源を活用して事業を進めることができるようになるだろう。
面白いことに相互支援関係は、支援された人が今度は支援する側にまわるという具合に勝手にどんどん広まっていくものである。相互支援の輪は、始めは一人が誰かを支援するところから瞬く間に会社に広まっていくだろう。 |