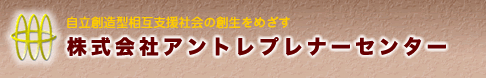「福島さん、うちの会社は新しいことを提案しても実現できるような風土がない会社なんですよ。まず上司がなかなかわかってくれないし、何とかわかってくれたとしても今度は実行するときに誰も助けてくれないんですから」
「それは困りましたね」
「まあ、困っているというよりも、もうあきらめましたね」
「ところで先日、まったく反対のことを上司が言っていましたよ。あなたが手伝ってくれないって」
いろいろなところで次のような疑問をよく耳にする。
(1) なぜ、部下は言うことを聞かないのか?
(2) なぜ、自分がやろうとすることを周りが助けてくれないのか?
(3) なぜ、うちの会社の職場は暗いのか?
(4) なぜ、こんなにも自分だけ評価が低いのか?
人間社会には一つの法則がある。それは「自分がやったことが自分に返ってくる」という法則である。他人が自分に対して何をしてくれるのかは、自分が他人に何をしてきたかの裏返しということだ。「他人は鏡」なのである。
さてこの法則に基づいて先の疑問を解明してみると、それらの答えは以下のようになる。
(1) 部下が言うことを聞かないのは、自分が部下の言うことを聞いていないから。
(2) 周りが助けてくれないのは、周りがやろうとすることを自分が助けてこなかったから。
(3) 職場が暗いのは自分が暗いから。
(4) 自分の評価が低いのは、自分が価値を提供できていないから、または他人の評価を高める支援をしてこなかったから
また、ビジネス社会は経済システムがどのように変化したとしても、相互に関わり合いを持つ人の集団であることに変わりはない。それは企業と個人の関係でも、社会と企業の関係でもまったく変わらない。この法則は人間社会である以上あらゆる場面に当てはめることができるのである。
顧客のために尽くすから、顧客から感謝されるのであり、社会に価値を提供するから、売上となって返ってくるのである。
人間の法則がビジネスの基本原則なのである。 |