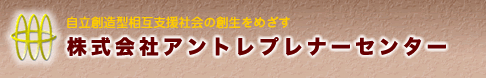メンター(Menter)とは「相手の持つ可能性を最大限に発揮させる支援ができる人」の ことである。自発的に能力を最大限に発揮する自立型姿勢の人材を育成することができる のがメンターだ。そして、最高のメンターとは、そこにいるだけでみんながやる気になる ような人のことである。
メンターの人材育成に対する基本的な姿勢は「自ら見本となって行動し、相手を信頼し て支援する」ことである。
以下このことについて詳しく説明してみよう。
1.見本となる
見本となるということは、まず自分自身が自立型姿勢で前向き積極的に物事に取り組む ことである。
メンターを単に精神的支援者と訳することがあるが、それはメンターの本質ではない。 メンターはまず自分の姿勢で示さなければならない。つまり、自らの姿勢によって相手に 動機付けをするのである。
子供に勉強させたかったら、自分がまずおおいに仕事を楽しむことである。毎日仕事を 終えて家に帰るたびに、
「ああ、今日も一日仕事が楽しかった。また明日も早く会社に行きたいなあ。子供の頃た くさん勉強しておいて本当に良かった」と言えばよい。
同じように部下に対しても、仕事は積極的に楽しんでやるものだ、と言う前に自分自身 が積極的に楽しんでやることである。他人に勇気を与える最も良い方法は自分がまず勇気 を見せることだ。最高の教育・人材育成とは自分の行動・生きる姿で示すことである。
メンターは自立型姿勢を行動によって示すことによって、尊敬されるような人々のこと である。いわばメンターとは相手から与えられる権威だ。その意味で「自称メンター」は 偽物ということになる。
2.信頼する
信頼とは相手のすべてを受け入れることである。そのためには、相手に問題があるのではなく、すべては自分に問題があると考える必要がある。考え方を変えることによって相手のすべてを受け人れることができるようになるからだ。たとえば、仕事はできて当たり前だと思えば、毎日が部下に対しての不満となり、部下に対して怒るだけになる。しかし、仕事はできなくて当たり前と思えば、毎日が部下に対して褒めるだけになる。
また、信頼とは期待と対峙する考え方である。期待が相手を思いどおりにしようとするのに対して、信頼とは相手にすべてを任せることである。期待と信頼の大きな達いは、信頼が相手から裏切られることさえも前提としている点である。
「信頼関係をつくるためには、いっしょに飲みに行ってじっくり話し合ってコミュニケーションを取ればよい」と言う人がいる。ところが飲みに行く回数が多い人々ほど互いに信頼し合っているかというと、実際にはそうでもないことが多い。その理由は、コミュニケーションを図ると言いながら、実は上司が部下に自分の考えを押しつけているだけということが少なくないからである。
コミュニケーションを取ることによって信頼関係は生まれない。信頼関係は相手のすべてを受け入れる、つまり相手はどうあれ、こちらから信頼することによってしか生まれないものである。
3.支援する
支援の目的は相手をやる気にさせることであり、いわゆる管理とは対峙する考え方である。相手を管理、コントロールしようというのではなく、相手のために今できることをやるのが支援である。
たとえば企業の中では、上司は支援する対象であり部下も支援する対象でしかないと考える。さらには他部署であっても支援する対象ということである。そしてお互いがお互いに支援し合うことによって、結果としてそれぞれが自己の目標を達成できるようになる。組織の活性化とは互いに支援し合うことによって達成されるのである。
部下が自分を支援してこないことを嘆くより、その前に自分が部下を支援してこなかったことを反省しなければならない。
また、支援において大切なことは何を支援するのかという内容よりも、支援しようという気持ちを持つことである。なぜならば何を支援したかということよりも、どんな思いで支援したのかということが相手に伝わってしまうからだ。何も手伝うことができないから、何も手伝わないということが一番の問題である。
そして、相手に対して私たちができる最高の支援とは「励ます」ことである。この「励ます」ことはどのような状況でもできるはずである。 |