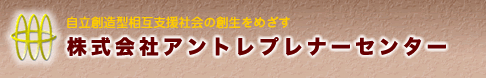私たちは安楽を求める欲求と充実を求める欲求の両立しえない相反する二つの基本的欲求を同時に持っている。
安楽の欲求とは人間が生命体として本能的に持っている欲求で、食欲・睡眠欲・性欲など生命を維持し子孫を繁栄させるために必要な欲求である。さらに物欲、支配欲、私利私欲などはこの欲求の延長にある。
安楽の欲求は極めて強い欲求である。それにまるで重力のように私たちを引きつけてやまず、生きている限り取り去ることはできない。しかし生きるうえではなくてはならないこの欲求も、社会生活の中では大きな問題を引き起こす。
安楽を求めるほど私たちは他人のことよりも自分のことを優先するようになり、自分にとって利益にならないことはやらないようになってしまう。さらに目先の利益に流され、長期的な展望の中で行動することをしなくなる。
安楽の欲求に基づいて働くことは、他人や企業に依存し、楽して得を取ることばかり考え、仕事上では生産性を上げることよりも報酬を得ることが行動目的になる。
たとえば企業活動の中でも、以下のように考えるようになる。
・面倒なことは避けたい
・自分に責任が回ってくることを恐れる
・新しいこと、やったことのないことにチャレンジするのは面倒
・休日休暇が待ち遠しい
・生活保障や休日休暇、快適な職場環境等を会社に期待する
・会社や上司に迎合する
・楽な仕事をしたい
・高い評価を得たい
・自分の思いどおりに部下を動かしたい
・自分の利益にならないことはやりたくない
これらの考えによって、行動すると以下のようになる。
・他部署や部下、顧客に責任を転嫁する
・トラブルの処理が遅れる
・指示がなければ行動しない
・いつでも働くふり、忙しいふりをする
・能力が向上しない
・仕事の改善、向上が遅れる
・不平、不満ばかりが口に出る
・部下や顧客から尊敬されない
・企業の生産性が低下する
こうして周りからの信用を失い、結果として自分自身も楽ができないということになる。
人間社会の基本構造は他人の役に立つことによって結果として報酬が得られるようになっており、安楽の欲求に基づいた社会性のない自己中心的行動では報酬をも得ることはできない。何とも皮肉な話かもしれないが、楽を求めるほど楽になれないのが人間社会なのだ。
企業の活力が失われるというのは、社員の意識がこの安楽の欲求に流されてしまうことをいう。 |