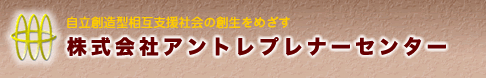ポリシーとは企業活動の行動基準である。ポリシーがないと企業内の価値観はバラバラとなり、組織としての統一的行動はできなくなる。企業は同じポリシーのもとで行動する集団でなければ、どれほど整備された形としての組織であったとしても最大限にその機能を発揮することができない。
ポリシーは企業内におけるあらゆることに優先しなければならないのである。
1.ポリシーは経営者よりも優先する
ある中堅企業の役員の方からこんな話を聞いた。
「うちの社長はワンマンなのはいいんですが、一つ困ったことがあります」
「どんなことですか」
「それはいつも気分で物事を判断することなんですよ」
「それは困りましたね」
「以前とまったく正反対の判断でも平気でするようでは、社員の意識を一つにするなんてことはとてもできません。できる社員がどんどん辞めていってしまいます。残るのは社長の顔色をうかがいながら、要領よくやっていこうという者ばかりになっていくような気がするんです」
「そうなるでしょうね。なんたって、社長の今の気持ちがポリシーなんですから」
社長が社長たる理由はポリシーを最も実践しているからということに尽きる。他の誰よりもポリシーをよく理解し、そしてその実践に努めているから社長なのである。
仮にそうではなく、社長の気持ちがポリシ−であるとするならば、社員は社長の顔色をうかがいながら仕事をするだけになるだろう。そのあげく自分で判断することができなくなり、自発的な行動をしなくなってしまうに違いない。
ポリシーとは社員一人ひとりが自分で考えて行動するために必要な行動基準なのである。
2.ポリシーは常識よりも優先する
不況と言われるアパート建築業界で成長し続けるハウジナ・コーポレーションは、所有者に対して二○年間の入居保証をし、また入居者にはボーナス併用払い可、敷金・礼金および退去時の修繕費無料、という業界の常識を打ち破ったまったく新しいシステムを提供して大変な注目を集めている。
社長の旗禮泰永氏はこう言っている。
「私たちの基本的なポリシーは、大家さんも入居者も社員も、みんなを幸せにするというものです。誰かだけの幸せであってはなりません。だからこういうシステムがあってもいいし、これまでなかったことが不思議なくらいです」
業界の常識が社会の非常識になっていることがよくある。その業界の中で当たり前と思われていることでも、顧客の側から見たり、社会の流れの中から見ると、いくらでも改善の余地が見つかる。つまりポリシーを持つということは、業界の常識に左右されないで物事を判断すると言うことである。
ポリシーが次代の新事業を生み出す基準となるのである。
3.ポリシーは利益よりも優先する
企業の利益第一主義が企業の存在価値そのものを否定してしまうことは以前にも述べたとおりである。確かに企業は利益がなければ成り立たないかもしれない。しかし、だからといって利益が出れば何でもやるというのでは、社会にとって意味のない、いや社会に弊害をもたらすことにもなりかねない。
たとえどんなに利益が出る仕事があったとしても、ポリシーに合わなければその仕事は断るべきである。利益なくして企業の存続がないのではなく、ポリシーなくして企業の存在価値はないのである。 |