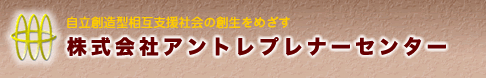では、企業におけるビジョンとは、どのようなものをいうのであろうか。ここでは、企業のビジョンの条件について考えてみたい。
企業のビジョンは何でもいいというわけではない。ビジョンが意味のあるビジョンであるためには、以下の四つの条件を満たす必要がある。
第一社会性
ビジョンは社会に貢献するものでなければならない。企業のビジョンとは社会の中における活動目的であり、その達成が社会にとって賛美される必要がある。そのためには、社会的な価値を生み出し、人々に感動を与えるものであることが求められる。ビジョンは誰からも共感されるものでなければならないのである。
第二具体性
ビジョンは具体的で明確なものでなければならない。具体性のない抽象的なビジョンほど達成できないものである。具体性のないピジョンでは、そこに関わる人が何をどうしてよいのか分からなくなるからだ。何をどうすることなのかを、はっきりと誰にでも分かるようにするためにビジョンは具体的にイメージできるものにしておかなければならない。企業トップの頭の中だけにあるビジョンは現実化しない。
第三困難性
ビジョンは簡単に達成できるものであってはならない。簡単に達成できるものであるならば、誰も本気になって達成しようとは思わないからだ。大きな困難を伴うものであるからこそ、その達成のためにみんなが本気になってカを合わせていくのである。
第四希少性
企業のビジョンはその企業独自のものでなければならない。一般論ではない、その企業ならではのオリジナリティが求められる。企業独自のものであるからこそ、そこに共通の価値観を持つ人々が集まるのである。 |