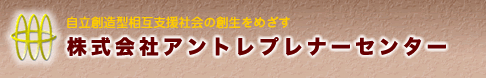|
以前、私は新宿に事務所を構えていたことがあるが、そこから一○○メートルほど離れたところに駐車場があった。そこにはいつでも元気で明るい、六○歳を過ぎたばかりの管理人のおじさんが働いていた。毎日のように顔を合わせていたが、いつもおじさんは明るい笑顔で挨拶をしてくれた。以前は大手企業で働いていたそうだが定年になって退社し、 そして駐車場の管理人の仕事を始めたということだった。
ある雨の日、駐車場に車を止めたとき、私は傘を忘れたことに気づいた。車の中でどうしたものかと考えていたところヘ、スタスタと管理人のおじさんが近づいてきて、「傘を忘れたんなら、これ持っていきなよ」と、自分がさしている傘を私にさしだしてくれた。
「でも、それっておじさんの傘じゃないの?今日の帰りは遅くなるから、おじさんがいる時間に返せないよ」
「いいんだよ。私のことはどうでもいいから持っていきなよ」
「じやあ、後ですぐに返しに来るから少しの間だけ貸してください」
管理人のおじさんはいつもこんな調子で、自分のことよりも他人のことばかり考えてくれるような人だった。
その駐車場は時間貸しもしていたが、場所柄もあってか、いつも満車の状態だった。そんなとき、管理人のおじさんは駐車しようとして入ろうとする車の運転手に、いかにも申し訳なさそうに謝っている姿をよく見かけた。そして必ず、道路に出てその車が見えなくなるまで少し薄くなった自髪の頭を深々と下げている。
そんなある日、寂しそうな顔をして、
「福島さん、実は今週いっぱいでこの仕事を辞めることになりました。妻が胸を悪くしたので、空気のきれいなところでのんびり暮らすことにしたんですよ。いろいろお世話になりました」と言って、頭を下げた。
「え、それは残念だなあ。でも、いろいろお世話になったのは、こっちのほうですよ」
私は何ともいえぬ叙しさを覚えた。
今日が最後というその日、私はちょっとした感謝の気持ちで手みやげをおじさんに持っていくことにした。駐車場に着くと、私はびっくりするような光景を目にした。管埋人室は駐車場の端っこにあって、やっと二人くらいが入れるくらいのプレハブ。その管埋人室は花束がいっぱいで中がまるで見えない。さらに置ききれなくなった手みやげがドアの外に高く積まれてあった。
「おじさん、じゃまになるかもしれないけど、これもここに積んどくよ」
「いやあ、どうもすみません。何の気遣いもいらないのに申し訳ありませんね。私はこの仕事をして毎日毎日がとても楽しくて、とっても幸せでしたよ」
「おじさんはどんな仕事をしたって、みんなに喜んでもらえる人なんだよ」
つまらない仕事なんかない。その仕事にかかわる人の姿勢が仕事を面白くしたり、つまらなくしたりしているにすぎない。私はそんなことを管理人のおじさんから学んだ。
仕事が面白いとか、仕事がつまらないというのは、その人が面白くなるように仕事に取り組んでいるか、つまらなくなるよう取り組んでいるかで決まるものである。楽しくやろうと思えば何でも楽しくなってくるし、イヤイヤやれば何でもイヤになってくる。
私たちは仕事の価値をそれにかかわろうとする姿勢によってつくっている。つまらない仕事だと決めつければ、その瞬間にどのような仕事でもつまらないものとなってしまう。つまらない仕事だと思い込んで取り組んでいると、必然的に仕事の生産性は落ちてくる。つまり、その仕事を通して社会や他人に価値・感動を与えることができなくなるのである。仕事にかかわる前に、私たちはすでにその仕事の価値を決めているといえるのではないか。
このことは、今どんな仕事にかかわっていたとしても同じである。
一流大学を出たのに、毎日がコピー取りの仕事ばかりと言って嘆いている若手社員の声を聞くことがある。こんなことをするために大学を出たんじやないと。でも、よく考えてみてほしい。コピー取りの仕事ってそれほどまでにつまらない仕事なのだろうか。
私はあるベンチャー企業の女性スタッフのこんな声を聞いたことがある。その人は仕事のほとんどがいわゆる雑務ばかりであった。電話応対に始まり、銀行へ行ったり、コピーをとったり、社内の清掃をしたりと結構忙しい。にもかかわらず、彼女はとっても毎日楽しく仕事ができるという。
「私の仕事はいわば雑用ですよね。みんな嫌がることかもしれません。でもみんなが嫌がることをするってとても気分がいいんですよ。自分が他の人の役に立っているって感じるじゃないですか。そのためにも、一つひとつの仕事の意味を考えるようにしています。この仕事をするとだれが喜んでくれるかを考えるんです。もちろん相手は声に出して喜んでくれるばかりとは限りません。でも、それはかっこ悪いと思っているからじゃないかと思うんです。心の中ではきっと喜んでくれているはずなんですから」
いまかかわっている仕事の面白さは、自分の仕事に取り組む姿勢によって決まるのである。 |